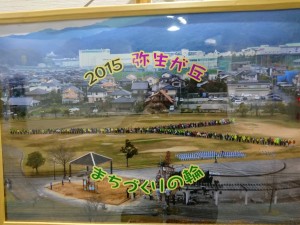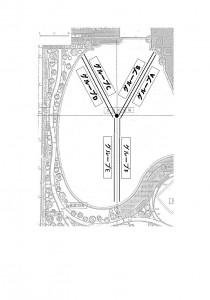独り言・・・選挙に行く意味
(独り言) 選挙に行く意味
2月17日鳥栖市長選挙です。
私の住む弥生が丘。前回の県知事選挙の時の投票率、なんと23%。
個人的に、、前代未聞の投票率でした。
投票所で、朝6時半から投票箱を開票所に届けるまで14時間の勤務。
虚しい。
「選挙に関心がないんだから行く理由がわからない」
「鳥栖で仕事してないし、そもそも関心がない」
「誰に投票していいか分からない、どっちも知らない人だし」
「私が投票しても何も変わらない」
投票に行かない人、行っても意味ないと思っている人の気持ちはよくわかります。
しかし、自分の気持ち。
「投票に行ってほしい」
なぜ?。
それは、町の事、自分の住む地域のことをもっと知ってほしいから。
地域のことにもっと関心をもってほしいから。
自分の住む町にもともっと関心をもってほしいから。
選挙に行って、町の事、地域のことをもっと話をしてほしいから。
隣近所の人と、地域の人と、仲良くなってほしいから。
そうすることで、自分の住む町はきっといい街になります。
町の仕事に携わりながら、そう思っています。
選挙に行く意味。
世間で言うほど簡単じゃない。
しかし、選挙に行くことで、町は変わります。いい街にすることができます。
誰がいい、かれがいいじゃない。
選挙に行く意味は、そこにあるような気がしています。
町の事、地域のことにもっともっと関心を持ってほしい。
選挙、行ってくださいね。
私も祐太郎を連れて選挙に行きます。
その意味わかるかな、、、?