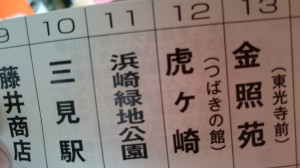2016年 5月2日から5月4日にかけて、開催された萩往還マラニック 250㎞に参加してきました。
開催数日前は、絶好調の感じで、タイムも40時間くらいでいけないかなぁ なんて甘い考えもありましたが、
蓋を開けてみると、やっぱり、史上最高というか、私の今まで経験した中で、もっとも過酷な、きつい大会でした。
なんとか走り終わって、まだまだ、修業の余地を感じ、私としては本当にかけがえのないいい経験をさせてもらったと感じています。
結果は、すべてのチェックポイントをクリアし、タイムも残り3㎞ちょっとで、残り時間35分と、ほぼ制限時間内完踏を目の前にして、撃沈し、時間は48時間を超えてしまいました。
一応、撤収中のゴール付近にたどり着き、記念写真。ちょっと寂しかったけど、人生ってこんなもん。ちょっとほろ苦い経験でした。
また次を頑張らないとね。
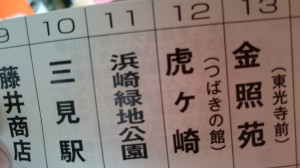


レースは、5/2 18:00~ 数十人づつのウエーブスタート。
私はたぶん第4組あたりで、エイエイオー!! の掛け声で、18:06分ごろのスタートになりました。
スタートの前日、仕事が終わらず、午前1時まで仕事、午前5時には起床して仕事の続き、、という、少しハードな前日を過ごし、
会場入りしてからも、いくつか仕事の処理をしながら。15:00ぎりぎりに説明会会場に到着。
その後、仮眠・・を考えていたんですが、その時間も作れず、18:00スタート。かなり、ねむーい感じのスタートになりました。

前半というか、一晩目は、暑ーい ランになりました。
最近、熱中症に弱いな。。と感じている私にとっては、初日から、きつーいランになりました。
それでも、時々、体温上がっちゃったなー と感じたら、歩きながらクールダウン。そして、ゆっくりリスタート。
体調も万全に感じていなかったので、ゆっくりとはいうものの、おそらく相応というか、ゆっくりが精いっぱいのスピードだったかもしれません。
上り坂の続くコースで、なかなか距離が進まず、22-3㎞の地点ですでに3時間(夜9:30を回ってました)あまり、イヤー先は長いなー と感じさせられました。
そして、明け方になり、漸く長門抜け、俵島へのルートに到着、(旧油谷中:87㎞地点)を通過、午前6時過ぎ。
午前7時ごろ、海が見えてきたころ、雨が降り出しました。
本日の過酷な一日の始まりです。
その後、雨は午後4時くらいまで降り続き、合計約9時間。雨に打たれながらはしりました。
俵島を過ぎて、立石観音、千畳敷と向かうところでは、完全に暴風雨状態。
正面、横から容赦なく強風が吹き付け、気を緩めると飛ばされそうになるくらいの、風雨でした。
私の経験した中では、史上最悪のランニングコンディションでした。
昨年の140㎞のときにも、一晩雨に打たれ、ついてないなーーとおもっていたのに、さらに強烈な悪天候。。。なんてこった。

それでも、暴風雨の海岸沿いを何とかクリアし、日置エイドを通過し、次のチェックポイント 湯元温泉へ向かいました。
しかし、この時点で、何㎞?おそらく、130-40㎞を走ってきていて、体のぼろぼろ感は、今までで最高レベルに。(初めての経験領域に入るので当たり前ですが)
ラン友のリタイヤの連絡も入り、私自身も頭の中で、リタイヤの文字がちらついてました。
でも、「とりあえず、止まらずに進んで、タイムアウトならしょうがない」
そう思いながら、湯元温泉のチェックポイントに到着。すると、神の声が、
この次の静が浦のチェックポイントが悪天候のため、キャンセルになったとのこと。
前半の最大の休憩ポイントである、宗頭文化センターまであと20㎞あまり、その中の約12㎞がショートカットされることを知りました。
まさに天の声。もう少し、頑張る気持ちを取り戻し、仙崎公園での記帳を終え、宗頭文化センターへ向かいました。
しかし、全く走れず、ほとんどを歩いて、宗頭文化センターに向かいました。
結果、当初明るいうちに、ここまでこれてたらいいなと思ていたのに、ここのチェックポイント到着は午後9時30分過ぎ。
想定より、だいぶ遅れて到着。
それでも、残り75㎞に20時間近い時間を残し、なんとか行ける。。と思いながら、
欲しくてほしくてたまらなかった、仮眠を約1時間とり、
午前0時ごろ、宗頭センターをリスタートしました。

あと75㎞。体は、痛いけど、みんな一緒。
頑張るしかない。
暗ーい 夜道を、一緒になった人たちと、なんとか駆け足スタイルで、進んでいきました。
三見駅(ここで10分ほどの仮眠)を抜け、夜の音だけの海岸沿いを萩市内方面を目指しました。
走らなきゃ・・・でも、足が動かん。が、独り言で、悶悶としながら、前へ進んで行きました。
そして、午前7時ごろ何とか、虎が崎に到着。

ここで名物のカレーを大盛でいただき、7時20分ごろ、虎が崎を出発し、東光寺経由で、萩往還道に向かう道に入りました。
この時点で、残り、45㎞ で残り時間10時間30分あまり。
きついけど、なんとか行けるだろうと、前へ進みました。

そして、午前9時ごろ萩往還道に入り、
明木のエイドに到着したのが、午前10時ごろ? なかなか進まない足に苦労しているところで、
電話が鳴っているのに気づき、家内から、義母の訃報を聞きました。
走る前から、悪いのは分かっていたので、驚きはありませんでしたが、
義母から頂いた選別のカロリーメイド ジェル(リンゴ味)があったのですが、
食べると逝ってしまいそうな気がしていたので、大事に大事に、後ろのほうにとっておき、
午前3時過ぎ、走りながら食していたところでした。
食べちゃったかなラナーなどと思いながら、
あとは、完踏するしかない。。そのな思い出、走りを続けました。
午後、3時、佐々波エイドで、関門ギリギリでクリアし、時間的にかなり厳しくなっていることを知り、
そこからは、気合を入れなおし、走り続けました。
途中、先輩方からのアドバイスもあり、
夏木原のキャンプ場をなんとか、ぎりぎりの午後4時50分ごろ通過し、
これで。完踏間違いなし。を確信しました。
しかし、ことは思うように行かないもので、
萩往還道の最後の石畳を抜け、最後3㎞ちょい 残り時間35分。
走り出しましたが、なかなか、足が思うように動かず、歩き出してしまいました。
ここで、10分我慢して走ることが出来れば、制限時間内に完踏で来ていたのに、、、が後の祭り。
歩くと、体温が上がり、おまけに、背中にせおっていた水が底をつき、
走れない状態になってしまいました。
結果、制限時間内のゴールをあきらめ、
完踏のみを目指し、制限時間と少々時間がかかってしまいましたが、ゴールまでたどり着きました、
走行距離 238㎞ 48時間と20分くらい。
残念でしたが、かけがえのない経験をまた一つさせていただきました。
萩往還マラニックのスタッフの皆さま ありがとうございました。感謝です。
アー眠かった。終わり。

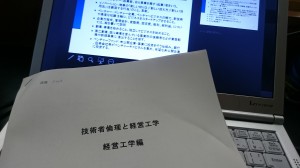



![DSC_1735[1]](https://makeyblog.pacjp.com/wp-content/uploads/2016/07/DSC_17351-300x168.jpg)